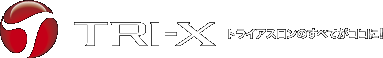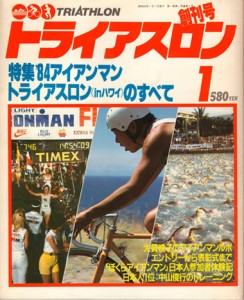日本トライアスロン物語
※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させる為、若干の脚色を施しています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。
第4章その2
安全対策が普及の鍵だ

その第一歩が1984年5月18日に東京・代々木の岸記念体育会館で開かれた「第1回トライアスロン(複合種目)連絡会」である。佐々木を代表幹事とする陸上、水泳、自転車などトライアスロン競技に関わるスポーツ界の指導者や、医学会などの研究者、それにアイアンマン・ハワイへの出場経験を持つトライアスリート達が顔を揃えた。
「気象条件も違えば、ロケーションも異なる。ならば、陸上競技のマラソンと同じだけれど、マラソンが42.195Kmと決められているのに対し、トライアスロンは大会によって距離がまちまち。だからタイムの比較も出来ない。それに計測方法も整っていないし、第一、参加選手達の健康と安全の管理が余りにも不備である。こうした点からトライアスロンが記録に挑戦する競技スポーツとして成り立つかどうか? さらに、トライアスロンが抱える問題を克服していく為の中央組織も、全く存在しない」
佐々木秀幸は、こうしたトライアスロンの特性や現状に対し憂慮していた。だからといってトライアスロンを否定していた訳ではない。むしろ、水泳・自転車・陸上の3種目を、ほぼ連続的に長時間に及んで行う運動は、記録的に行き詰まり状態にある長距離競技やマラソン選手達のクロス・トレーニングとして有効ではないかと考えていた。
「それにしても、トライアスロンをより良い道へと誘導するコントロール・タワーを整備する必要がある」
1982年2月のアイアンマン・ハワイで女子選手のジェリー・モスが四つん這いになりながら劇的なゴール・シーンを世界の人々に見せて以来、国際的なトライアスロン・ブームが到来し、日本でも次々とトライアスロン大会が開催されていく状況を垣間見ながら、佐々木や橋本治朗はトライアスロンの普及、発展の為の諸条件を整備することが必要不可欠と思った。そこで佐々木は陸上、水泳、自転車などトライアスロン競技に関わるスポーツ界の指導者らと共に、一時、中断していた「トライアスロンを考える会」の会合を再開し、トライアスロン競技に関わる研究討論を重ねる一方、トライアスロン組織創りの具体的な検討を始めたのだ。
その第一歩が1984年5月18日に東京・代々木の岸記念体育会館で開かれた「第1回トライアスロン(複合種目)連絡会」である。佐々木を代表幹事とする陸上、水泳、自転車などトライアスロン競技に関わるスポーツ界の指導者や、医学会などの研究者、それにアイアンマン・ハワイへの出場経験を持つトライアスリート達が顔を揃えた。この会合では、全国的に広がり始めたトライアスロン大会の情報を収集する中央センター設立の必要性が訴えられた。
次いで翌6月4日の第2回会合を経て、同じく6月24日の日曜日に東京・千駄ヶ谷の国立競技場内クラブルームにおいて全国連絡会発足の為の「準備委員会総会」が開催されたのである。この時、集まったのは佐々木を始め村田統治や浪越信夫、それに橋本や佐野など発起人グループと、東京医科大学助教授(当時)の岩根久夫、東海大学教授の中見隆男、それに熊本CTCの永谷誠一やJTRCの矢後潔省らトライアスロン・クラブの代表者、その他ジャーナリストなど35名である。
この席で挨拶に立った佐々木は、組織創りの課題を次のように語った。
「トライアスロンを普及させていくには、何よりも選手達の安全性を確保していかねばなりません。この視点を欠いてしまったら、普及も発展もありません。その為に競技ルールや大会ロケーションの整備を図る中央的な組織の設立が必要不可欠だと思います。それは全国のトライアスロン選手達の為の、選手達による組織でなければなりません。その前段として、今年中に全国のトライアスロンの代表者達が集う連絡協議会を発足したいと考えています」
いわゆるナショナル・ガバニング・ボディの在るべき姿が提起されたのである。日本トライアスロン協会(Japan Triathlon Association=略称JTA)は、その後、約2年後に設立された。
《次回予告》日本トライアスロン協会(JTA)の前身である「複合耐久種目全国連絡協議会」の発足と、代表幹事に就任し、後にJTA会長となった清水仲治氏(故人)の思い出を語ります。