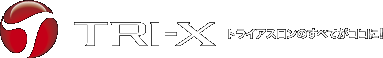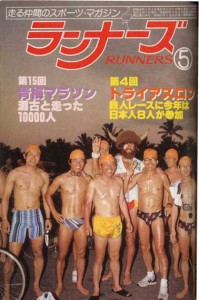日本トライアスロン物語
※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させる為、若干の脚色を施しています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。
第1章その6
好奇心が強く自立心が旺盛な男たち

いかにしてトライアスロン出場を諦めさせるか、その根拠となるデータを採るつもりで日本を出立した私が、ホノルルから成田に向かう機内では、どのようにして安全に競技を行わせるかを真剣に考えているのに気がつき、苦笑せざるを得ませんでした
”人類の極限への挑戦”と謳った第4回ハワイ・アイアンマン大会に参加した日本人8名のうち、先頭でフィニッシュしたのは当時、神奈川県鎌倉市に在住していた会社員、勝尾 弦(32歳)だった。
トータル・タイムは12時間44分15秒で総合101位である。東京・晴海のドゥ・スポーツプラザのトレーニング仲間で日本人2位だった西澤 孝(28)のタイム14時間02分40秒、同170位を時間にして1時間以上、差をつけた。初めてのトライアスロン、しかも日本人が過去に誰一人として経験したことのない海外で行う初めてのスポーツ競技、何もかも初めて尽くしながら、勝尾は見事な成績で完走したのである。
それでいて勝尾は、自分なりにこのハワイの大会を楽しんでいた。今時のトライアスリートはトランジション・タイムを少しでもロスなく短縮しようと必死な形相で着替えているが、勝尾たち日本人選手はトライアスロンというスポーツを存分に楽しむこと、そして自分流のやり方で完走を果たすことが最大の目的で、タイムを競うという概念には乏しかった。
それにしても勝尾のバイクは速かった。バイク・コース約180Kmはアップダウンが繰り返し続き、しかも太陽を遮る樹木は見当たらず、気温は35度以上にものぼる灼熱の世界だが、そこを勝尾はおよそ6時間半で走り切ったのだ。コース途中での体重チェックやエイドステーションでの休憩タイムを除くと、全行程を時速、約30Kmで走破したことになる。その間、勝尾を抜いた選手はわずか1人、あとは追い抜くばかりだったという。おそらく当時のトライアスリートでアイアンマン・ディスタンスのバイク・パートを、このスピードで走り抜ける者は少なかったであろう。
高等学校2~3年生の時代は自転車競技部に所属、国体への出場は叶わなかったものの、団体ロードレース競技で東京都3位に入るなど、サイクリストとして鍛えた成果が生きたと言うべきか。バイク終了時点で勝尾は総合40~50番手につけたが、次は苦手のランで、今度は抜かされる羽目になってしまった。ランも月間250~300Kmの練習量をこなしたのだが、過去に左脚の靭帯を切ったため練習量が300Km以上を超えると痛むので、それ以上できなかった。それでも、この大会のラン・パートを約4時間40分で走り抜き、日本人のトップでフィニッシュ・ラインを踏んだのである。
そのほか勝尾とともにドゥ・スポーツプラザを拠点にトレーニングを積んだ日本人選手たちも、海外で行う初挑戦のトライアスロン大会を自分なりに、その力を存分に発揮して見事、完走した。
西澤 孝は勝尾に続く日本人2位でフィニッシュしたし、村松鉄郎(28歳)も小林 登(38歳)と共に手をつないでゴールイン、堀川稔之(47歳)はバイクのメカ・トラブルに悩ませられたものの余裕を余して完走し、島田勇生(39歳)もフラフラになりながらフィニッシュ、それぞれ「鉄人」の称号を得たのである。
第4回ハワイ大会・日本人出場・完走者
勝尾 弦 12時間44分15秒 101位
西澤 孝 14時間02分40秒 170位
小林 登 14時間48分09秒 210位
村松 鉄郎 14時間48分09秒 211位
堀川 稔之 15時間27分22秒 238位
島田 勇生 17時間25分43秒 275位
永谷 誠一 19時間46分30秒 295位
堤貞 一郎 25時間44分02秒 298位
 勝尾はハワイから帰国する飛行機の中で、改め心の中で誓った。
勝尾はハワイから帰国する飛行機の中で、改め心の中で誓った。
しかし、その思いはすぐに砕けた。帰国後、会社の社長から呼び出され、
「そろそろ仕事をしなさい」
と言われたのである。以来、勝尾は国内、海外を含めトライアスロン大会に出場することはなかった。
「トライアスロンはお金と暇がないと、なかなかできない贅沢な競技ですね。でも、今でもジョギングは続けていますよ。土曜・日曜の休日は1時間半くらい、距離にして10Km~15Kmくらい走っています。自宅近くの梨畑の道をね」
勝尾が言う通り、第4回ハワイ・アイアンマン大会に出場した日本人8名は皆、「好奇心が人一倍強くて、自立心が旺盛な人たち」だった。しかし、その後もトライアスロンを長く続けたのは永谷誠一、1人だけある。
【次号予告】日本人8名の中の最年長者・堤 貞一郎の奮戦振りなど第4回ハワイ大会のフィナーレをお送りします。
※この物語は歴史的事実を踏まえながらも、ストーリー性を加味させるため、若干の脚色をほどこしています。しかし、事実を歪曲したり、虚偽を記すことはありません。また、個人名はすべて敬称を省略しています。
<トライアスロン談義>トライアスロン界の恩師・岩根久夫先生 【桜井 晋】
日本のトライアスロンの歴史を語るとき、トライアスロン界の父である堤 貞一郎先生とともに、わが国のトライアスロン・ドクターとして活躍された東京医科大学の岩根久夫教授(当時は助教授)のことを忘れてはならない。堤先生は1983年の第3回皆生トライアスロン大会のスイムで事故に遭われ死亡されたが、岩根先生は97年9月、教鞭を執る東京・新宿の東京医科大学の校舎にて過労からか脳溢血で倒れ、10日後に死亡された。享年64歳だった。
その岩根先生がトライアスロンと初めて接触したのは、やはりハワイ島で行われた第4回大会である。当時、東京・新宿のドゥ・スポーツプラザのフィットネス施設内の診療所でクラブ会員に対しカウンセリングを行っていた時、ハワイ大会に出場しようという勝尾 弦氏と西澤 孝氏の2人が相談やってきたのだ。大会前年の1980年10月のことである。
西澤氏は知る人ぞ知る蝶々の蒐集家。蒐集先のパプアニューギニアで、マラリアの特効薬クロロキンが効かない抗クロロキンマラリアにかかり79年に入院、九死に一生の末、退院するという病歴があるだけに、トライアスロンへの挑戦は内心、不安でもあった。そこで同じ東京・晴海のドゥ・スポーツプラザの「ミリオンメーター・スイミングクラブ」のトレーニング仲間である勝尾氏に相談したところ、岩根ドクターに相談してみようということになったのだ。しかし、2人の話を聞いた岩根先生は、
「そんな、無謀なことはやめなさい」
と、即座に否定したのだった。でも2人の心は、すでにハワイに飛んでいた。
「せっかくだから、やります」
ドゥ・スポーツプラザを経営する日新製糖(株)の社宅が東京・豊洲にあり、そこを拠点に村松鉄郎氏や堀川稔之氏らとともに、猛烈なトレーニングを積み重ねてきた2人である。簡単に諦め切れるものではない。2人の決意を聞いた岩根先生は、無言のまましばらく考えていたが、
「では、皆さんの身体をみてあげよう」
こうして勝尾氏をはじめとする晴海のドゥ・スポーツプラザ会員だった4名、それに堀川氏が経営する会社の社員の後輩に当たる島田勇生氏と小林 登氏の合計6名が再び岩根ドクターを訪ね、全員、血液検査を受けたのだった。検査の結果は、肝機能が一時的に低下していた堀川氏を除き全員合格だったが、それでも心配の虫が収まらなかった岩根先生は、トライアスロンの医学的・科学的データの収集とトライアスロンの生命に及ぶ危険性を知らしめようと、彼ら6名とともにハワイへ同行することを決心した。こうして岩根先生のトライアスロン選手に対する血液採取と医学的研究活動が始まったのである。
岩根先生の愛弟子であり岩根先生の遺志を受け継いで、トライアスロンの医科学的研究を続けておられる東京医科大学教授の勝村俊仁氏は、当時の様子を次のように振り返る。
「医科学の立場から申し上げると、トライアスロンというスポーツが人間の身体に悪影響を及ぼすことは自明の理でしたが、当時はそのエビデンス(証拠)がありませんでした。それで岩根先生は、血液検査などを行い実際に証明しようとハワイに行かれたのです。心電計をはじめ注射器や採血容器などをカバンに一杯、詰めて行きましたが、血球成分を血清と血漿とに分ける遠心分離器は持参できませんので、コナ病院の検査技師に協力を依頼しました。
その頃、私は岩根先生の研究を傍らで見ていただけでしたが、面白そうな研究でもあり、ハワイ島も楽しそうなので、3年後の1984年から岩根先生に同行し、以来、毎年アイアンマン大会へ行くようになりました」
そしてまた勝尾氏は、岩根先生の思い出を次のように話す。
「岩根先生にはスポーツと医科学のことをたくさん教えていただきました。私たちの血液を採取し、その結果を逐一、報告してくださいましたが、その一例として、脳下垂体から分泌する麻薬様な物質βエンドルフィンがトライアスロンという長時間に及ぶ運動を続ける源泉になっていること、というかβエンドルフィンが過酷な運動を続ける肉体の防衛機能を担っていることなどをお聞きしたのです。実際、第4回大会で岩根先生が検査した私たちの血液中βエンドルフィンの分泌量は、スタート時よりもフィニッシュ時の方が10数倍も上昇していたそうです。このβエンドルフィンの分泌に関わる研究成果は、岩根先生が民間レベルの研究として世界で初めて明らかにしたものではないでしょうか。しかも岩根先生はハワイの遠征費用も、またその後、たびたび行った私たちの血液採取並びに検査にかかる諸費用も、すべて自費でまかなわれました。私がフィニッシュした時、先生が『勝尾くん、よくきた、よくきた!!』といって本当に喜んでくれた顔を、今でも忘れることはできません」
トライアスロンが始まって四半世紀を経た。この間、私はトライアスロンに関する文章を読み、かつまたトライアスロン界の多くの人々と接触し、トライアスロンの生命と文化の歩みを学んできたつもりである。その過程で今なお私の胸に染み入る文章がある。トライアスロンのことを描いた数多くの文章の中で、かくも美しく、トライアスロンの何たるかを見事に表現した文章である。それは、岩根先生が日本人8名の選手とともに第4回ハワイ・アイアンマン大会の現地へ乗り込み、そこで遭遇した光景を後にランナーズ社発行の『トライアスロン入門』の中で述べた手記だ。
岩根先生が不慮の事故で亡くなられてから早や6年半ほどになる。かつて岩根先生と新宿の酒場で酒を酌み交わしトライアスロンの将来について語らった思い出を想起しつつ、先生が書き認めた文章を紹介したい。
「まる24時間に及ぶ、長い長いトライアスロン・デイでした。体は疲労していましたが、床について目を閉じた私の網膜に、くっきりと焼き付いた光景がありました。それは、人影もまばらになった夜中の3時過ぎに、ようやくたどり着いたアメリカ人選手と、彼を迎える奥さんと子供の姿でした。3人は抱き合い、何回も何回もキスを繰り返したあげく、人気のなくなった街を肩を並べて帰っていきました。その彼らの背に、無人のフィニッシュラインの真上にかかる月が、優しく光を投げかけている光景は、一瞬、私の心の琴線に触れる何かを感じさせました。決して良い成績ではなかったけど、この苦しい競技に打ち勝った父親の姿は、小さな坊やにはどんなに大きく見えたことでしょう。父は無言でゴールし、子供も無言で父に抱きつきました。私には持ち合わせない、無言の教育を見た心地がしました。いかにしてトライアスロン出場を諦めさせるか、その根拠となるデータを採るつもりで日本を出立した私が、ホノルルから成田に向かう機内では、どのようにして安全に競技を行わせるかを真剣に考えているのに気がつき、苦笑せざるを得ませんでした」(桜井 晋著『新トライアスロン入門』1989年6月発行)