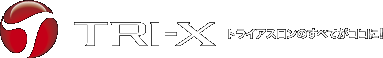白石トレーナーから教えられたこの言葉は今も深く心に残っている。
世界で活躍した選手達は非常識とも思われるトレーニングに挑戦し、それをやり遂げ、やり続ける。現在の多くのアスリートは「科学的トレーニング」という言葉に惹きつけられ、誤魔化しのトレーニングに取り組んでいるケースが多い。
科学的トレーニングって何だろう?
誰かが非常識なトレーニングをする。失敗すれば「バカな練習」と言われてお終しまい。
成功すれば、それを分析し、更に理由付けをし「科学的トレーニング」と称される。
すなわち、これが科学的トレーニングと言われるものの実態だ。
(もちろん理論先行の科学的トレーニングも存在する。)過去に、トレーニング中は水を飲むとバテるので、水分補給は禁止されていた。
過去に、野球選手は肩を冷やすから絶対に水泳練習はダメだといわれた。
過去に、水泳選手は関節が硬くなるのでウエイトトレーニングはダメだといわれた。
インターバル・トレーニングを初めて実践したE・ザトペック選手は当時は陸上界の笑いものだった。
それがあるときを境に「科学的な練習」と称される。
そのことに気づいていない選手はまだ多い。
1日わずか24時間しかないので、それを効率良く有効に使うために「科学的トレーニング」が必要になる。しかし現実を見てみると、練習時間をフルに使ってもいない選手が、怠けるために科学的トレーニングという言葉を使って逃げているのが現状だろう。
少なくとも私が身近でみることができたアスリート達は違っていた。有森裕子(五輪2大会連続メダリスト)、斉藤仁(ソウル五輪・金メダリスト)、鈴木大地(ソウル五輪・金メダリスト)、松岡修三(テニスプレイヤー)の姿は当時の私の大きな衝撃を与えた。誰も行わないようなトレーニングを積極的に実施していた。
ヒーロー工房という場所に居たからこそ、生々しい姿を見ることができた。話を聞くことができた。彼ら、彼女らの戦う姿勢が私の根本的な考え方に大きな影響を与えてくれた。
「世界とは何か」「どこまでやれば届くのか」「何が勝負を分けるのか」
世界で勝ち抜いた選手達の練習は、非常識ともいえる練習が多く含まれていた。
常識に囚われている限り、自分の限界は打破できない。
身体的に劣る日本人が世界で勝ち抜くことは難しい。
難しいかもしれないが、世界を目指すのであれば早めにこれを理解し、実践してほしい。
既に「世界」は限界までトレーニング量を増やしたアスリートで満ちている。
量が増やせなくなった現在、質を重視し、更にその「次」の練習方法を模索している段階だ。
この「次」が見つからないうちに、練習量だけでも負けないアスリートになってほしい。
 白石トレーナー(右)と宇城師範(中央)。山梨学院の名監督・上田誠仁氏(左)の更に上を行く達人2名だ。科学的トレーニングの「その次の方法」を見出すための大いなる挑戦をしている先人達だ。
白石トレーナー(右)と宇城師範(中央)。山梨学院の名監督・上田誠仁氏(左)の更に上を行く達人2名だ。科学的トレーニングの「その次の方法」を見出すための大いなる挑戦をしている先人達だ。
 山梨学院大学の上田監督。陸上界にありながらトライアスロンを非常によく研究してくれている。山梨学院大学が初めて箱根駅伝に参加した時代に私も合宿に参加させてもらった。
山梨学院大学の上田監督。陸上界にありながらトライアスロンを非常によく研究してくれている。山梨学院大学が初めて箱根駅伝に参加した時代に私も合宿に参加させてもらった。
4年間しかない大学生活の中で結果を残させることも達人技といえよう
中山俊行プロフィール
 中山俊行(なかやま としゆき)
中山俊行(なかやま としゆき)
1962年生まれ
日本にトライアスロンが初めて紹介された18歳のときトライアスロンを始める。
日本人プロ第1号として、引退までの間、長年に渡りトップ選手として活躍。
引退後も全日本ナショナルチーム監督、チームNTT監督を歴任するなど、日本の
トライアスロン界をその黎明期からリードし続けてきた「ミスタート ライアス
ロン」。
【主な戦績など】
第1回、第2回 宮古島トライアスロン優勝
第1回、第2回 天草国際トライアスロン優勝
1989年から8年連続ITU世界選手権日本代表
アイアンマン世界選手権(ハワイ・コナ)最高順位17位(日本歴代2位)
初代・全日本ナショナルチーム監督
元・チームNTT監督
元・明治大学体育会自転車部監督