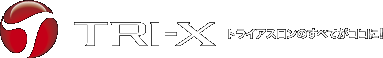トライアスロン・シーズン真っ只中である。競技として挑む選手、自分自身に挑む選手、どちらにとっても戦いの最中にいる。暑いからといって、エアコンの効いた部屋でノンビリすることができないのはトライアスリートの悲しい習性だ。
五輪を目指す選手にとっては勝負どころ。8月12日のワールドカップ・ハンガリー大会までのポイントが世界選手権代表資格獲得に係わる上に、その世界選手権は目前で9月上旬に開催される。そして世界選手権の結果は北京五輪へとつながってゆく。日の丸を背負う選手達を応援してあげてほしい。
全国各地でも日曜日ごとにレースが開催されている。MSPOを見ても日曜日が開けるごとに、いくつものレースリザルトが掲載されている。「トライアスロンって人気のあるスポーツなんだ」と思いつつも、ふと考える。
ランニングには昔から根強い愛好者がいる。ここ数年は、普通のランニングばかりでなく、山岳ラン、トレイルランの人気も高く、著名な大会は定員オーバーで出場することすらできない。オープンウォータースイムの大会も多く開催されている。大盛況だ。自転車においても空前の自転車ブームにより、イベントの人気が高まってきている。
一方、トライアスロンに目を向けてみる。いくつかの地方大会が終わりを告げる。一部の大会を除いて、定員割れが当たり前のように発生している。エリートレースに至っては参加者が少なすぎて、そのレベルすら怪しくなりつつある。新しい大会もいくつか開催されてはいるが、トライアスロンが衰退傾向にあることは認めたくない事実である。その理由はどこにあるのだろうか。「会員5万人計画」といって声を上げたところで登録者が増えているとは思えない。地方や現場に目を向けて現実を把握した上で計画を練らなければ無意味な計画になるだけだ。参加者、主催者の声はモチロンだが、これから挑戦したいと思っている隠れた一般アスリート達の気持ちを理解して具体策を実行しなければ競技人口の増加は望めないと考える。超初心者向けの大会、女性向けの大会、子供向けの大会、、、現時点で「トライアスリートではない」人達をいかにしてこの競技に引き込むか。そこがキーポイントである。
じゃあトライアスロンは落ちぶれてゆく駄目なスポーツなのかというと、そんなことはない。一部の大会では大盛況。
盛り上がる大会と、衰退する大会。この差はどこにあるのか。
大会にポリシーがある大会は廃れない、と良く耳にする。これは主催するサイドの大きな課題でもある。開催地の熱意が大きい大会は人気が高い。しかしながら他人任せな大会ほど迷路に迷うケースが多いのではなかろうか。もちろん交通の便や道路事情など、現実的な課題が大きな影響を与えることも事実ではある。
しかし大会のポリシーが明確であれば、賛同した選手はリピーターとなり、その大会に繰り返し出場しようと考える。大会色がはっきりしなければ一回参加して満足して終わってしまう。
有名選手を呼んでみたり、タレントに頼ったり、大会の公認をもらうことだけでは限界がすぐにきてしまう。何がその競技をメジャーにするのか、今一度考えてもらいたい。
「トライアスロンをメジャーにする」。私にとっても悲願である。
・・・考えてみると「自分のポリシー(ファイトスタイル)」を明確化している選手の方が強い。

神奈川県・日米親善トライアスロン大会。1000人近い参加者+その応援者で、集まる人数の合計は何人になるのだろうか。「トライアスロンは人気がある」と自信が持てるような大会だ。
それを支えるマーシャル&役員達。こういう人達の活動がトライスロンを盛り立てる。

ハッキリ言って競技レベルは高くない。しかし楽しい。表彰される人数も多い。順位など終わってしばらくしないと判らない。それでも「自分の力で走りきる」というトライアスロンの原点を重視するのが、この大会の特徴だ。
中山俊行プロフィール
 中山俊行(なかやま としゆき)
中山俊行(なかやま としゆき)
1962年生まれ
日本にトライアスロンが初めて紹介された18歳のときトライアスロンを始める。
日本人プロ第1号として、引退までの間、長年に渡りトップ選手として活躍。
引退後も全日本ナショナルチーム監督、チームNTT監督を歴任するなど、日本の
トライアスロン界をその黎明期からリードし続けてきた「ミスタート ライアス
ロン」。
【主な戦績など】
第1回、第2回 宮古島トライアスロン優勝
第1回、第2回 天草国際トライアスロン優勝
1989年から8年連続ITU世界選手権日本代表
アイアンマン世界選手権(ハワイ・コナ)最高順位17位(日本歴代2位)
初代・全日本ナショナルチーム監督
元・チームNTT監督
元・明治大学体育会自転車部監督